観察7 気孔のはたらき(蒸散)
2002 5 17(金)
理科室
(上: 沈丁花の気孔 ×600)
・ 細胞までよく観察できる
・ 葉緑体も見える
<授業の流れ>
1 前時の復習
→ 維管束の並び方まで
2 蒸散についてプリントにまとめる
(1) 根から水を吸収する
(2) 維管束(道管)を通って体全体にいきわたる
(3) 余分な水を気孔から出す(蒸散)
(4) 気孔は葉の裏側にある
(上:Aさんの学習プリント)
3 気孔を観察する
手 順
1 沈丁花の葉を引き裂いて、裏側の薄片をつくる
(上:薄くはがれた部分を観察させる)2 スライドガラスにのせる
3 カミソリの歯で必要な部分だけを切り取る
4 水を1滴かける
5 カバーガラスをかける
6 不要な水を吸い取る
7 顕微鏡で観察する(低倍率(7×10)で良い)
8 スケッチする
9 発見したことをまとめる
(上: 2人の生徒のスケッチ)
・ 右のスケッチは、気孔の周りの細胞が2つになっていない
ワセリン(植物の油)を使った実験について
1 ワセリン(植物の油)を使った実験については、教科書の説明にとどめる
2 これは、気孔が『葉の裏側』にあることを証明する実験である
3 この実験を行うより、実際の観察に時間を使ったほうが効果的である
4 実際に、気孔が『葉の表』にないことも顕微鏡により確認できる
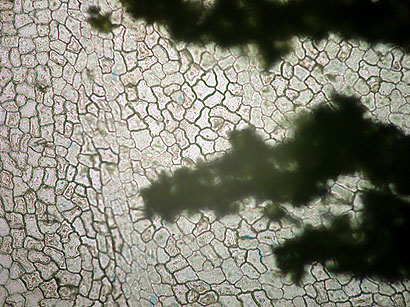
(上:葉の裏の細胞)
・ 気孔は見当たらない
・ 右にある黒い陰は光合成を行う細胞達である
<評価基準>
1 自然事象への関心・意欲・態度
2 科学的な思考
3 実験・観察の技能・表現
A 表皮細胞のプレパラートをつくり、気孔を観察スケッチすることができる
4 自然事象についての知識・理解
B 気孔と蒸散について正しくまとめることができる
授業を終えて
学校の花壇に沈丁花があったので、その葉を引き裂いたところ、簡単には薄片をつくることができた。顕微鏡で観察すると、たくさんの気孔(しかも葉緑体)が観察できたので、それを教材にすることにした。
(上:校庭にある沈丁花、若葉なので試料として扱いやすい)
・ 指導書や教科書に紹介してある『ツユクサ』は季節が早すぎるし、小さい
・ 『ジンチョウゲ』ならいくらでもあるし、表皮細胞を剥がしやすい
・ お勧めです