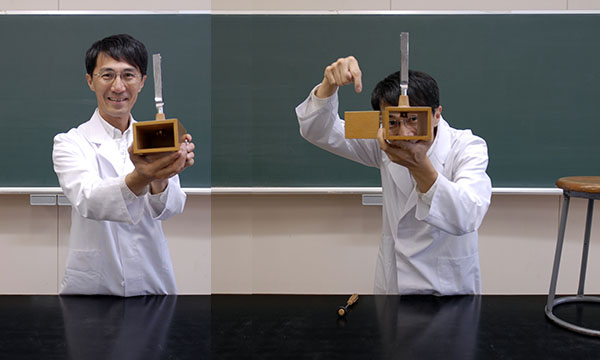| このページは中学校1年理科『物理』/takaの授業記録2002です |
実験12 糸電話、音叉(おんさ)
2003 2 17(月)
第2理科室、校庭
小学校までに糸電話で遊んだ経験のある生徒は、各クラス数名以下でした。それなら1時間遊ばせても良いのですが、きちんと時間をとって発見・感想をまとめさせることで、遊びが科学に変わります。しっかり実習させたいのですが、理科に割り当てられた年間授業時間数が限られているので、泣く泣く授業後半にまとめ、そして、音叉の学習を行いました。
2023年6月追記
音叉に関する授業記録を調べたところ、記述内容が弱い。写真も少ない。そこで、本ページに音叉に関する内容を追記しました。

上:先生は高度な遊びになるように見守ります。
<授業の流れ>
1 糸電話の原理
「糸電話で聞こえるのは何故でしょう?」
・ 紙コップの底が振動するから
・ 紙コップの中の空気が振動するから
・ 声で空気を振動させるから
・ 糸があるから
・ 糸が振動するから
・ 耳があるから
2 糸電話で遊ぶ
<注意点>
・ 難しいことを言わない
・ 糸の長さを50mにしても聞こえる
・ 糸はピンと張らないと聞こえない
・ 盗聴することもできる
・ 糸を結び直してもよい
・ 紙コップに穴をあけなくても良い
・ セロテープで止めるだけでよい
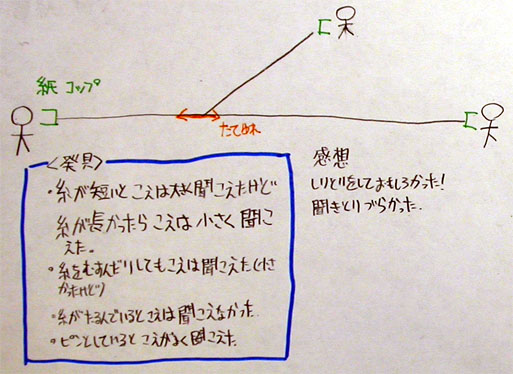

(上:なかなかのアイデアです)
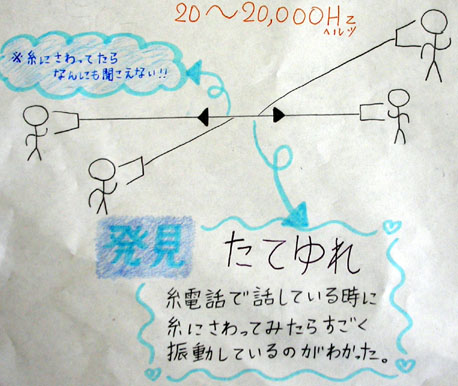

(上:両耳につけると、非常に良く聞こえます)
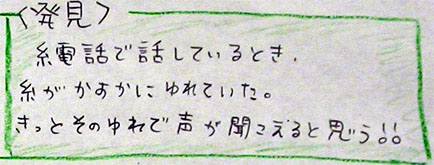

(上:糸が絡まっても、さらに面白くなることもあります)

「それでは、教室に戻りなさい。」
「感想と発見をプリントにまとめなさい。」
「5分後に、音叉の実験をします。」
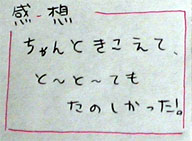
3 音叉を使った「共鳴」、「うなり」の学習
音叉の学習内容は3つです。1つめは音叉と共鳴箱の紹介、2つめは音叉の共鳴、3つめは音叉によるうなりです。
|
(1)音叉と共鳴箱の紹介
1)音叉を共鳴箱から外し、
2)音叉を叩く。
3)そして、音叉だけではあまり聞こえないことを確認する。
次に、
4)音叉を叩き、振動している共鳴箱の中心に当てると、
5)途端に、音が大きくなることを確認する。
|

上:音叉を共鳴箱に取り付け、音叉を振動させるMr.Taka
音叉は一定の振動数で振動、共鳴箱は音叉の振動を増幅
この音叉は振動数440Hz(ラの音)
|
|
(2)音叉の共鳴
1)音叉を共鳴箱に取り付け、2つ並べる(距離:70cm)。
2)そして、一方の音叉を叩き、
3)叩いた音叉を止める。
すると、
4)叩いていない方の音叉が鳴っていること確認する。
5)音叉の距離を2mほど離して、共鳴実験を行う。
6)音叉の距離を5mほど離して、共鳴実験を行う。
※共鳴箱の口を、互いに正確に向け合うとよく共鳴する。
共鳴は音叉ではなくても、振動数が同じ物体どうしなら起こる。
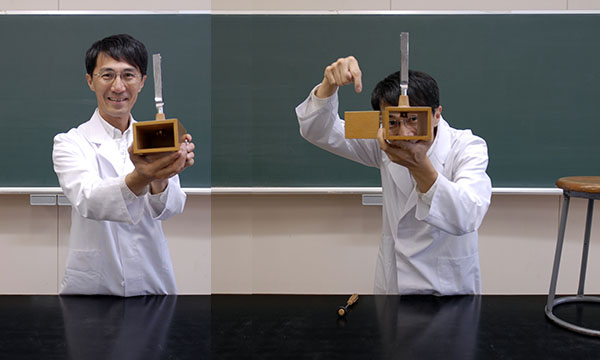
上:共鳴箱にある蓋を開くと、空気を振動させることができない=音が出ない。
|
| |
(3)音叉のうなり
1)共鳴箱に固定した音叉を2つ並べる(距離:70cm)
2)一方の音叉に重りをつける

(上:手前の音叉には黒い重りが付いている)
3)叩いて、音が低くなったことを確認する
4)その理由を確認する
次は、音叉に重りをつけます。」
「どんな音になるでしょう。」
「音の大きさは、ほどんど変わりませんね。」
「何が変わったのですか?」
「良く、聞いて下さい。」
「重くなったので、振動数が変わるから、、、叩きますよ。」
「分かりましたか?」
「そうですね、振動数が減って低い音になりました。」
|
5)一方を叩いても、他方が共鳴しないことを確認する
6)逆を叩いても、共鳴しないことを確認する
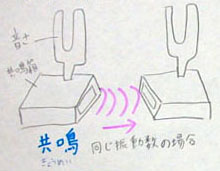 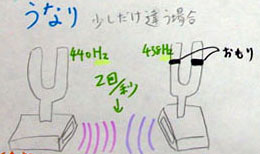
上2枚:振動数が同じ場合に共鳴する。
今回の実験に使用した音叉は振動数440Hz(ラの音)
一方におもりをつけると振動数が下がって共鳴しない。
|
7)両方同時に叩く
8)両者の間に『うなり』が生じていることを確認する
9)重りの位置を微妙に変えて、『うなり』の変化を確認する
10)9)をくり返して楽しむ
|

上:Cさんの学習プリント(部分)
|
◎ Dさんの学習プリント
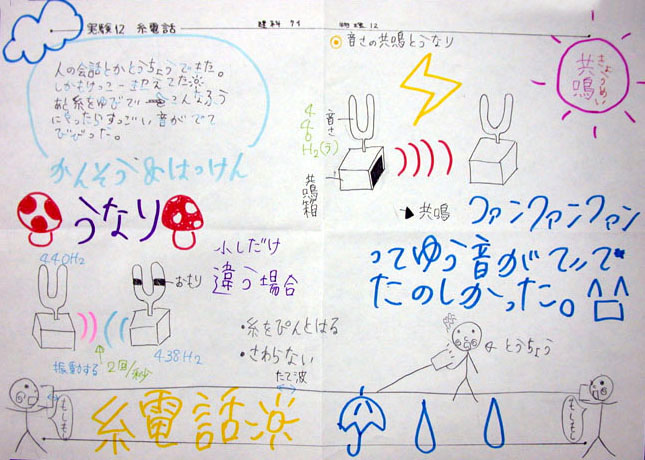
◎ E君の学習プリント
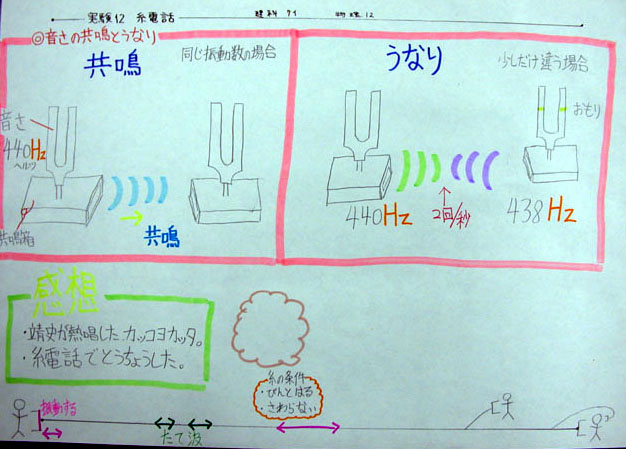
<評価基準>
1 自然事象への関心・意欲・態度
A 自宅から紙コップ、糸を持参することができる
B 糸電話で楽しく遊ぶことができる
2 科学的な思考
A 縦ゆれ(疎密波)が伝達するしくみを実験から確かめることができる
B 糸電話で音が伝わるしくみを実験から考えることができる
3 実験・観察の技能・表現
A 糸電話を発展的に工夫して実験することができる
B 性能のよい糸電話を作ることができる
4 自然事象についての知識・理解
B 音は、糸を通して伝わることが理解できる
B 音叉の共鳴とうなりについて正しく理解できる
授業を終えて
子どもは遊ばせておけば、いろいろな発見をする。それを放置すると幼稚な遊びで終わってしまうが、科学的にまとめ考察することで、より高度な遊びに発展する。理科の目標は遊ぶことかも知れない。
↑ TOP
[→home](C)
2003 Fukuchi Takahiro